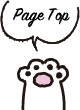「産後パパ育休」制度がスタート!パパがするべきことって何?
2022年10月6日
産後パパ育休が2022年10月~スタート
「育児・介護休業法」が改正され、2022年4月より順次施行されています。
男女ともに仕事と育児を両立できるよう、新たに「産後パパ育休制度」が創設され、2022年10月より施行されることとなりました。
産後パパ育休とは?
「産後パパ育休」とは、既存の育休制度とは別に、男性が子供の出生から8週間までの間に、合計4週間の育休を2回まで分割して取得できる制度のこと。
現行制度との違い
従来の「育児休業」は、原則、子どもが1歳になるまでに取得できるもの。
新たに施行される「産後パパ育休」は、育児休業とは別に取得できるもので、「子の出生後8週間以内に4週間まで取得可能」です。
それは分割して2回取ることもできます。(例えば2週間ずつとか)
これまでも父親が出産後8週間以内に育児休業を取得した場合に、育児休業を再取得できる「パパ休暇」があったけれど、出生後8週間以後に母親と途中で育休を交代するといった取得方法は難しいものでした。
産後パパ育休制度が創設されることで、より柔軟に父親が育休取得時期や期間を調整できるようになり、夫婦が育休を交代できる回数が増えることになるのです。
つまりは、パパが柔軟に育児休暇を取得できる仕組みができたということ・・・!
パパの育児休暇取得率
厚生労働省が発表した2021年度雇用均等基本調査によると、男性の育児休業の取得率は変動こそあるものの上昇していて、2021年では過去最高の13.97%となりました。
1996年度では0.12%だったというのでその伸び率に驚かされます。
政府目標として掲げているのが「2025年までに男性の育休取得率30%」だそう。
これまでよりも育休を取りやすい・歓迎される職場の雰囲気となることを期待します。
幸せいっぱい、でも大変。産褥期
どうしても閉鎖的になってしまいがちな産後の生活。
新生児のうちは本当にあっという間とはいえ、昼夜逆転の生活、果てしなく続く授乳、それらに伴う睡眠不足に細切れ睡眠、おむつの付け方が甘くて大惨事、ミルクの吐き戻しによる大量の洗濯物、忙しい夕方にやってくる謎の黄昏泣き、上の子の赤ちゃん返り・・・大変なことを挙げればキリがない(笑)
かわいくて、いい匂いがして、フニャフニャで愛おしい我が子なのです。かわいいのは重々承知なのですが、産後のこの時期は体のダメージもあり、精神的に不安定になるもの。
やっとありつけた食事の時に泣かれるとついついイラっとしてしまうなんてこともあるあるなのでは。
体が回復するまでは外出も控えなければならないということもあり、ますます新生児ママの孤独感は強まる傾向になりがちです。
そんな時、話せる大人の存在ってどれだけありがたいか・・・!
産後パパ育休という制度を有効的に利用し、頼れるパートナーと共に孤独感を解消しつつ快適に過ごしたいですよね。
パパの活躍こそママの幸福につながります
男性育休の現状~約3人に1人が「とるだけ育休」
2019年に公益財団法人 日本財団が「パパ・ママの育児への向き合い方と負担感や孤立感についての調査」を実施したところ、なんと育休中男性の約3人に1人が一日の家事・育児「2時間以下」という、ポーズだけの「とるだけ育休」の実態が浮き彫りとなり、数々のメディアで取り上げられ反響を集めました。けしからん!
同調査の結果、育休が家族の幸福感に直結するかどうかは、育休の「質」次第であることがわかりました。
男性育休の取得率や取得人数など「数」が注目されがちではありますが、真に注目すべきは家事育児の「質」!
産まれてくる赤ちゃんにきょうだいがいる場合は、パパは「育児の手伝い」ではなく「育児の主役」になることを目標としたいところです。
産後パパ育休中、パパがするべきこと
では、具体的に何をすればいいのでしょうか?
一例をご紹介します。
家事
言わずもがなズバリ家事全般です。
ママの身体の回復を第一に考えて、この時期はパパが家事を全面的に担いましょう。
メニューを考え買い物に行き、食事の用意をする、食後の食器洗いやごみの片づけまでが料理です。
その他に洗濯、風呂やトイレの掃除などなど。
ばりばりこなせるように準備も必要です。出産前からひと通り流れを実践することが大事です。
育児
パパが赤ちゃんと数時間でも二人だけで過ごせるように準備しておくと、いざという時慌てずに対応できます。
産後のママは乳腺炎など体調を急に崩してしまうこともあります。
そんな予期せぬ事態の時でもミルク・オムツ・着替えといった基本的なお世話ができると心強いですよ!
(上の子がいる場合)上の子のお世話
パパが面倒を見ることによって、ママが下の子のお世話に集中することができます。
普段忙しいパパならなおのこと、お子さんとの大事なコミュニケーションのチャンスです!
他にも保育園について調べたり、ママの仕事復帰後の生活について話し合ったり産休育休中にしておきたいこともたくさん・・・!
家事代行も家事育児のチームの一員に
初めての育児であればパパも戸惑ったり、疲れたりすることもあることと思います。
疲れが溜まると、ちょっとしたことでイライラして家庭内の雰囲気が険悪になってしまうことも。
一番大変なのはママですが、パパにも息抜きは必要です。
そんな時にぜひ家事代行を利用していただきたいです。
パパに余裕が生まれると、産後不安定になりがちなママの心に寄り添うこともできますよね。
「何かあった時」のために依頼者登録される方も多くいられますが、家事代行を上手に利用して、家族みんな疲れて果ててしまう前に活力を回復してはいかがでしょうか?
家事代行をご家庭のチームの一員として加えていただきたいと強く願っています。
おたすけママンはアナタの暮らしを応援します!